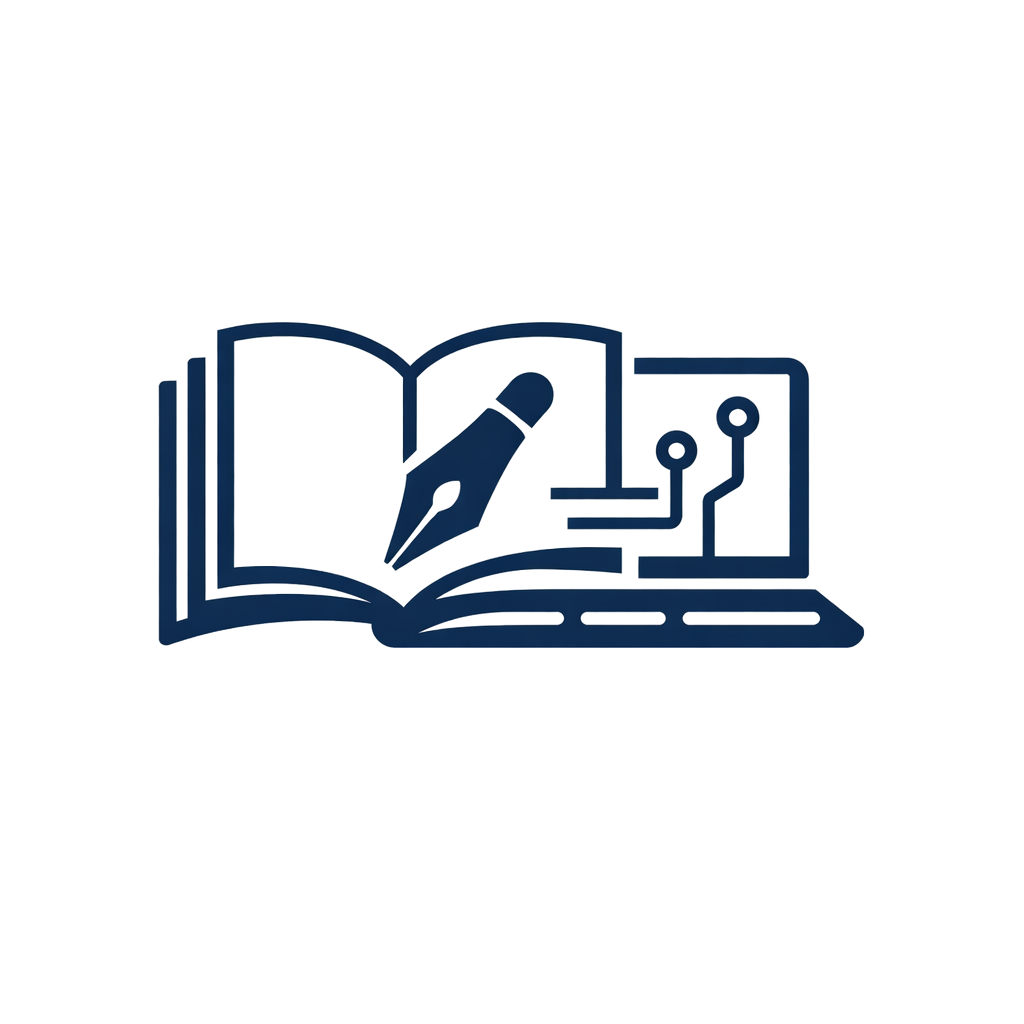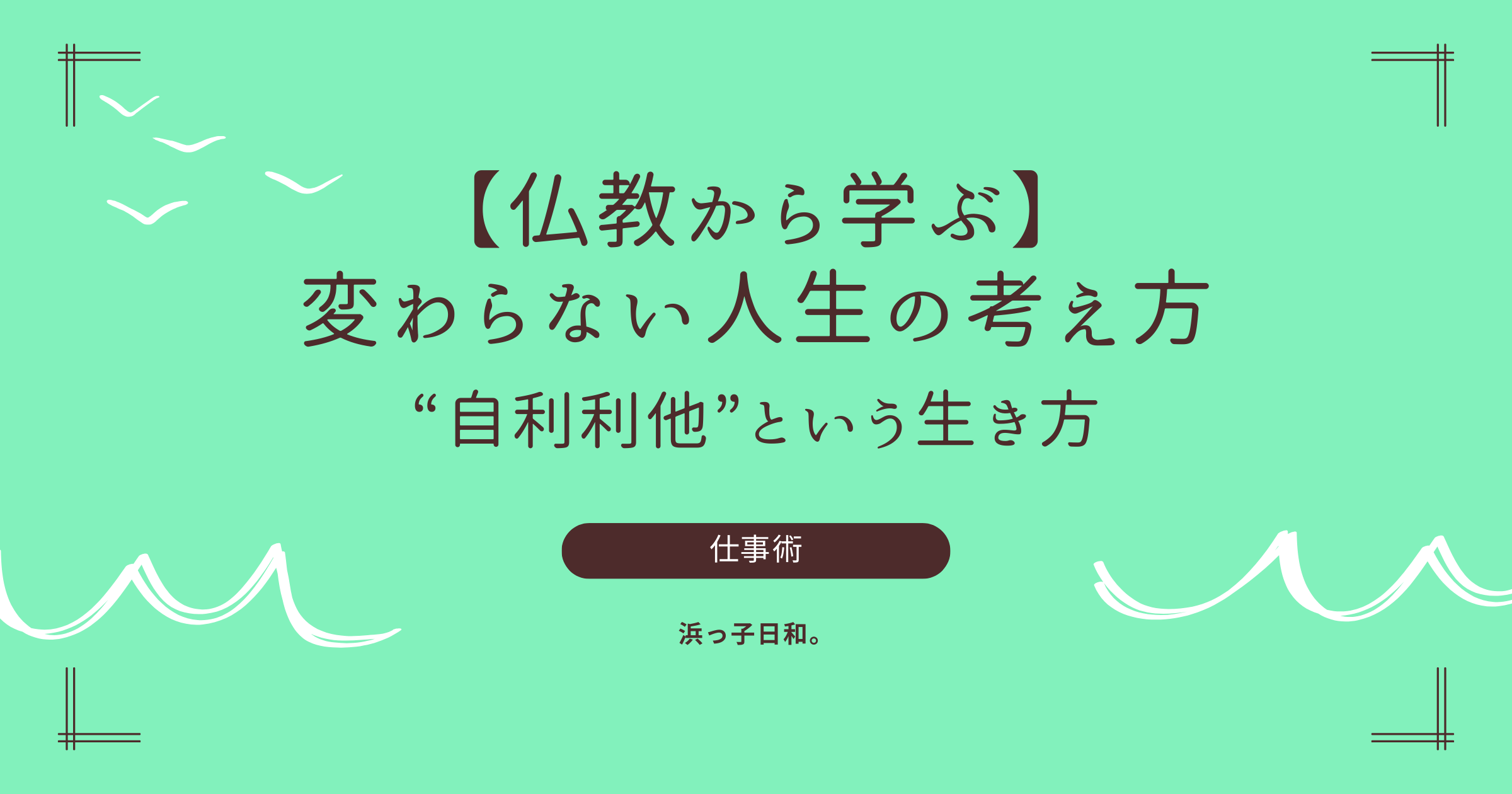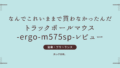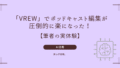テクノロジーが進化して、SNSでもいろんな考え方や思いを簡単に世の中に発信することができるようになってきていると感じています。
あの人はこんな考え方をしているんだって学ぶことももちろんありますが、多すぎて何を信じていいんだよってなっています。(笑)
そこで気になったのが、話題のマインドフルネス「禅」です。でもそれをやろうっていうか、仏教って面白いかもって思ったので、今回はここから一つ私が好きな教えをお伝えしたいなと思います!
それが 「自利利他(じりりた)」 の教えです。この考え方めっちゃ好きなので、ぜひ見てってください!
自利利他とは何か?
「自利利他」とは、自分の幸せと他人の幸せは切り離せないという仏教の教えです。
- 自利:自分を利すること。学びを深め、心を磨き、自己成長すること。
- 利他:他人を利すること。人にやさしく、相手の喜びや幸せを考えて行動すること。
つまり、自分の幸せを追い求めるだけでは不完全で、同時に他者への貢献があって初めて心が満たされるのです。
これって本当にそうかもって思ってて、確かにお金は全然もらえない仕事かもしれないけど、「ありがとう」って言葉が私はとても好きです。言ってもらえたらやってよかったなーって思っています。
仏教の逸話に見る「自利利他」
この自利利他の考え方が見て取れる仏教の逸話をいくつか調べてきたので、紹介します。
釈迦が病人を看病した話
お釈迦様が弟子と旅をしていたとき、病気の修行僧が放置されていました。
お釈迦様は自ら身体を清めて看病し、こう説いたといいます。
「誰もが老い、病み、死ぬ。だからこそ、互いに助け合わねばならない。
自分を大切にするように、他人を大切にしなさい。」
盲目の比丘と水たまり(詳細)
ある日、目の見えない比丘(修行僧)が、道を歩いているときに誤って大きな水たまりに足を取られ、身動きがとれなくなってしまいました。
周りには多くの修行僧がいましたが、その姿を見ても誰も助けようとしません。
すると一人の僧が足を止め、盲目の比丘に手を差し伸べて、水たまりから引き上げました。
その行いを見ていたお釈迦様は、周囲の弟子たちに向かって次のように説きました。
「仲間を助けるその心は、己の修行を深めることと同じである。
他者を救うことは、自分を救うことでもあるのだ。」
現代における「自利利他」の実践例
では、今の社会でどう「自利利他」を実践できるでしょうか。
具体的な生活シーンごとに考えてみましょう。
- 仕事において
チーム開発では「自分のスキルを磨くこと(自利)」が、そのまま「仲間や顧客の役に立つ(利他)」ことにつながります。 - 家庭において
親が健康でいること(自利)は、家族の安心(利他)につながります。
自分を整えることが、そのまま周囲へのやさしさになるのです。
このように「自分のため」と「他人のため」は循環し合い、どちらか一方だけでは成り立ちません。
よくある誤解と、その答え
自利利他という考え方は誤解されやすい部分もあります。
「自分を犠牲にしてまで他人を助けるのか」
自分を犠牲にする必要はないと思います。自分が満たされている状況でないと、他人に対しても何もしてあげられないですよね。風邪をひいている人に助けられても、風邪をうつされたくないし、心配が勝ちます。(笑)
あとは、自利利他にはもう一個誤解があって、「相手のためにやってあげた」と自分のエゴで終わらせないことです。
自分はこの人のために頑張ったと思っていても、もしかしたらおせっかいだった可能性もあります。「今じゃない、、、」タイミングの問題かもしれないですし、「このレベルだったら、、、」みたいにスキル不足もあり得ます。
自分のために頑張っていて、初めて他人を救えるのだと私は思っているので、自分のスキルを高めることはやめてはいけないと思って私も日々過ごしています!
「自分だけが幸せになればいい」の限界
現代には「成功すれば幸せになれる」「お金さえ稼げば満たされる」という考え方もあります。
しかし実際は、地位や収入だけでは心が安定しません。
他者との関わりや「誰かの役に立った」という実感があってこそ、深い幸福感を得られる。
これが仏教の説く「自利利他」の真髄です。
まとめ:普遍の教えをこれからの時代に
どんなに社会が変化しても、人の心の本質は変わりません。
- 自分を磨き(自利)
- 他者を思いやり(利他)
- その両方を大切にしてこそ、本当の幸福に近づける
私は「自利利他」が本質なんじゃないかなって思ったので、この考え方を信じていきたいなと思っています。
宗教っていうだけで、毛嫌いする人もいるかもしれませんが、目からうろこの考え方もあると思っています。仏教についてもう少し調べてみようと思うので、また参考になったら嬉しいです!